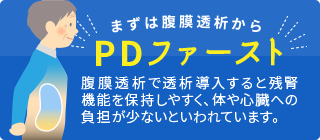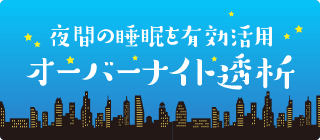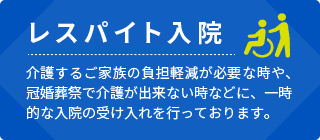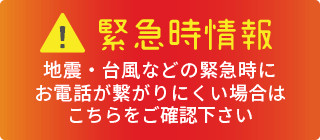麻酔科の概要
幅広い内科疾患に対応
糖尿病を伴う慢性腎不全や透析患者さんに対する全身麻酔は、とくにハイリスクとされています。大病院でも透析患者さんが全身麻酔下に手術を受ける割合は少なく、麻酔もハイリスクであるために手術が敬遠されることがしばしばあります。
当院は、手術対象の6割以上が透析患者であり(全国平均は1割以下)・7割以上が重症加算対象患者(全国平均は2割以下)であるにもかかわらず、術中・術後合併症発症率は一般病院と変わりありません。
手術を受けられる患者さんは、様々な不安をお持ちであると思います。しかし、皆さんが安全かつ快適に手術を受けて頂けるように、我々麻酔科医は尽力致しますのでご安心下さい。
経験豊富なスタッフの充実
当院の手術室スタッフは、透析や慢性腎不全に関する専門知識が豊富であり、ハイリスク患者さんの手術を多数経験しています。実際の手術時には、細心の注意を払いながら、個々の患者さんに合った最適な麻酔方法で、手術をおこなっています。つまり、当院は日常的に重症患者さんの手術に接しており、手術麻酔管理のポイントをスタッフ全員が熟知した専門病院といえます。
麻酔の種類
①全身麻酔
全身麻酔薬によって、完全に意識を消失します。手術中の記憶は一切残りませんが、人工呼吸器によって生命維持管理をおこないます。麻薬・静脈麻酔薬・ガス麻酔・筋弛緩薬などの様々な薬剤を適切に組み合わせて手術をおこないます。
②脊髄くも膜下麻酔(脊椎麻酔)
俗にいう、「下半身麻酔」です。背中に細い針を刺し、クモ膜下腔に局所麻酔薬を注入します。意識は消失しませんが、患者さんのご要望で手術中に軽く快適に眠れる鎮静薬を使用することも可能です。
③硬膜外麻酔
背中に若干太い針を刺し、硬膜外腔に細いカテーテルを挿入します。カテーテルから局所麻酔薬を注入することによって、術中・術後鎮痛効果の質が格段に向上します。全身麻酔と併用することもあります。
④伝達麻酔
俗にいう、「神経ブロック」です。超音波画像装置を用い、手術部位を支配する神経の周囲を局所麻酔薬でブロックします。近年、エコー装置の画質が格段に向上したため、安全かつ確実に手技をおこなうことが可能となりました。これにより術中・術後疼痛がかなり軽減できます。
医師紹介
坂本 元[主任部長]
坂本Dr.png)
■ 資格
麻酔科標榜医
日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医
日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
National Board of Echocardiography PTEexam 合格
National Board of Echocardiography CCEexam 合格
日本集中治療医学会集中治療専門医
臨床研修指導医
対象疾患・治療について
当院の外科系診療科は、外科・血管外科・整形外科・泌尿器科・眼科です。麻酔科医と外科系医師と常に連携を取りながら、個々の患者さんに適した手術や麻酔をおこなっています。
徹底したストレス軽減策
患者さんにとって、手術前後には様々なストレスが発生します。当院では、患者さんのひとつひとつのストレスに対応した、きめ細かい配慮を心がけています。
術後回復促進策
かつては、全身麻酔の前日~当日は長時間の絶飲・絶食・安静が強いられていました。現在は、それらは患者さんにとって苦痛であるだけでなく、術後回復を遅延させ、術後合併症を増加させることが分かっています。
当院では、絶飲食の時間を最小限にし、手術当日も1000Kcalの摂取を目標として、身体の免疫力アップを図っています。また、手術当日から早期離床をすすめており、術後のリハビリも積極的におこなっています。
麻酔科からのおしらせ
日本麻酔科学会麻酔科認定病院
2020年4月1日付で、当院は日本麻酔科学会麻酔科認定病院に認定されました。
つまり、当院は患者さんにとって快適かつ安全に麻酔管理がおこなうことができる施設です。
臨床研究
現在進行中の臨床研究はありません。しかし、当院ではよりよい医療の確立に貢献するために、今後の研究内容を模索しています。
術後疼痛管理チームの発足
2025年1月より、当院は本格的に「術後疼痛管理チーム」を発足しました。術後疼痛管理チームとは、麻酔科医・手術室看護師・薬剤師・臨床工学技士から構成されています。手術後の患者さんの術後疼痛管理対策が主な目的であり、手術翌日にチームで回診をおこないます。患者さんの痛みの評価を適切におこない、患者さんが創部の痛みが強い場合は、追加鎮痛薬の投与をおこないます。チームだけでなく、患者さんや病棟看護師も含めて、疼痛の質・鎮痛薬の使用状況などについての情報を共有します。